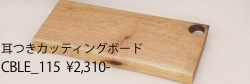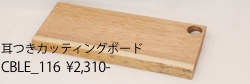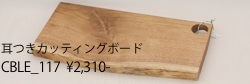HOME>家具屋で働く双子のブログ
家具屋で働く双子のブログ
耳つきテーブル用の板が使えるようにするための準備。【No.1363】
10月に材木市場で仕入れた耳つきテーブル用の板を整理しました。トラック一杯に積み込まれた板を整理するのにそれなりに時間が掛かってしまいますが、1枚1枚大きさを記録して写真を撮影しています。そして、乾燥前に必要な処置をしておきます。板はそのまま置いておいても我々が思っているようにはなってくれません。乾燥が上手くいくようにそれなりに時間と手を掛けて処置をしておく必要があります。
耳つき板を効率よく使用するためにやっておかなければいけないことがあるので、今日のブログではその点に触れることにします。
1.樹皮を取り除く
2. 割れ止め剤を塗る 既存の木口からの割れにカスガイを打つ
3.桟積みする
まず、やっておかなければいけないのは樹皮を取り除くことです。製材するときに樹皮を取り除く場合と取り除かない場合があります。樹皮を取り除く場合は、皮剥き機で荒っぽく取り除くことが多いです。製材するときに樹皮があると木の状態が掴みにくいのと樹皮に紛れ込んでいる石などで製材機の刃を傷めるというデメリットがあります。ただ、皮剥き機を使うと耳の部分がボロボロになってしまうため、耳つきで使うには皮剥き機で樹皮を剥がしていない板の方が良いです。また大きな丸太は皮剥き機に入らないということもあります。私が仕入れに行っている市場に出ている板は、樹皮がついたまま製材された板が多いです。これは耳つきで使う我々の場合はとても有難いです。
ただ、樹皮がついたまま置いておくとその部分に虫がついてしまいます。そのため樹皮はすぐに剥がしておかないといけません。樹皮をつけたまま長時間放置しておくと面白いように虫が喰います。樹皮と木部の間の部分を喰い散らかします。
続いてやるのは、割れ止め剤を塗ります。木口と板目の部分に割れ止め剤を塗るのが通常です。特に木口は水分が抜けるのが早いので、割れ止め剤を塗っておくのがよいです。木口付近は水分が抜けるのが早く、他の部分と差ができます。その差が割れの原因になってしまいます。幸い、この作業は板を市場に出品している方がやっている場合が多いです。割れ止めの為に塗る専用のものもありますし、木工用ボンドで代用する場合もあります。木工用ボンドを水に溶かしてそれを塗っていきます。ただ木工用ボンドはそれほど効果があるようには思いません。塗らないよりは効果が少しあるかなといった感じです。専用の割れ止め剤の中にはかなり効果があるものもあります。ただ、効果がありすぎてなかなか乾かないというデメリットもあります。
すでに木口から割れが入ってしまっている部分には、カスガイを打ちます。カスガイは鉄の棒をコの字に曲げた金具です。割れている所にカスガイを打っておけば割れが拡がるのを抑えることが出来ます。と言っても、カスガイが効かない割れもあるのでこれもおまじないのようなものと割り切っています。
そして最後は桟積みです。板を積む場合に間に桟を挟んで積んでいきます。乾燥は空気に触れさせることが大前提になります。そのため、板の両面が空気に触れている必要があります。1枚1枚の間に桟を入れることで空間が生まれて、板の両面を空気に触れさせることができます。

桟積みは木材を保管する際の基本事項です。桟を入れる間隔などで板の状態が変わることもあります。基本は入れる位置を揃えて桟が一列に並ぶようにします。ただし、長さが違う板を重ねることが多いのでうまく桟が並ばないこともあります。
このように乾燥させる前にいろいろと処置を施します。こうしておいてから半年~1年ほど天然乾燥させます。板を使用できるようになるまでにはこうした下準備が必要になります。あとは上手く乾燥してくれることを願うばかりです。
瑞木@相模湖
-
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (8)
- 2025年4月 (6)
- 2025年3月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (6)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (10)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (7)
- 2020年1月 (10)
- 2019年12月 (8)
- 2019年11月 (12)
- 2019年10月 (8)
- 2019年9月 (3)
- 2019年7月 (7)
- 2019年6月 (21)
- 2019年5月 (16)
- 2019年4月 (21)
- 2019年3月 (21)
- 2019年2月 (19)
- 2019年1月 (25)
- 2018年12月 (23)
- 2018年11月 (30)
- 2018年10月 (25)
- 2018年9月 (24)
- 2018年8月 (25)
- 2018年7月 (30)
- 2018年6月 (32)
- 2018年5月 (31)
- 2018年4月 (32)
- 2018年3月 (31)
- 2018年2月 (29)
- 2018年1月 (32)
- 2017年12月 (32)
- 2017年11月 (29)
- 2017年10月 (31)
- 2017年9月 (30)
- 2017年8月 (31)
- 2017年7月 (31)
- 2017年6月 (30)
- 2017年5月 (31)
- 2017年4月 (30)
- 2017年3月 (31)
- 2017年2月 (28)
- 2017年1月 (31)
- 2016年12月 (30)
- 2016年11月 (30)
- 2016年10月 (31)
- 2016年9月 (30)
- 2016年8月 (30)
- 2016年7月 (32)
- 最近のブログ記事
- オンラインショップ
お問い合わせContact
- TEL:0422-21-8487
- 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-28-3 2F
(営業時間: 12:30〜18:00/定休日:火・水曜日)