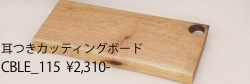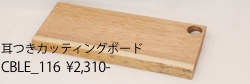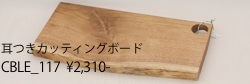HOME>家具屋で働く双子のブログ
家具屋で働く双子のブログ
オイル仕上げの木製カトラリーや木の器のすすめ。【No.1724】
先日のブログでオイル仕上げの無垢材テーブルが気になっているけど、シミや汚れ、メンテナンス方法などにも不安を感じている方はオイル仕上げのカトラリーや器を使ってみるのはどうだろうかという話を書きました。無垢材テーブルは決して安くない買い物なので、失敗はしたくないですよね。自分のイメージと違ったなんてことのないようにしたいものです。
→オイル仕上げのテーブルに不安を感じている方にはカトラリーやうつわから使ってみるのが良いかも。
今日はもう少しオイル仕上げのカトラリーや器について掘り下げてみようと考えています。いまや100円ショップでも木のスプーンなどが売られている時代です。大手量販店でも数百円で木のスプーンが売られています。そういうものの多くは中国産でウレタン塗装が施されているはずです。ウレタン塗装は水や汚れに強く、特に木を使うことなく使用できるのがメリットです。ただ、木の表面に塗膜を作って固まっているので木の質感が持っている本来の質感を味わうことができません。
せっかくなら木の本来の質感を味わってもらいたいものです。オイル仕上げは木の表面に塗膜をつくることがありません。導管の中にでオイル成分が固まるだけなので、木の質感を損ないません。ただ、水や汚れなどに弱くすぐにシミがついてしまったりします。このようなデメリットがあるため、大量生産品にはあまり使われることはありません。個人の木工作家さんが作るカトラリーや器はオイル仕上げのものが多くあります。もうひとつ、漆仕上げの製品もたくさん販売されています。本格的な漆器になってしまうとかなり高額になってしまうため普段使いはなかなかできません。しかし、木工作家さんが拭き漆で仕上げたカトラリーや器はそこそこの価格で販売されています。漆仕上げはとても強いのでウレタン塗装品と同じようにガンガン使用することができます。

オイル仕上げの木製製品は水で洗ったり、拭いたりするとオイル成分がだんだん抜けていってしまいます。オイル成分が抜けると白っぽくなります。上の写真は私が作って自分で使用しているオイル仕上げのウォールナット材のスプーンです。仕上げには食用の荏胡麻油などを塗っています。先端の口に入れる部分は既に白くなっていてオイル成分が完全に抜けてしまっています。オイル成分が抜けているとさらに汚れやシミがつきやすくなります。
こうなったら軽く#320程度の紙ヤスリで磨いて、再びオイルを塗って拭き取ります。

するとこのように元の姿に近い様子に戻ります。オイル仕上げのスプーンでカレーを食べるととどうしても色がスプーンに移ってしまいます。左のスプーンではカレーをなんども食べているので、黄色になっていました。カレー臭もついていましたが、何度か洗ったら気にならなくなりました。色はすぐには落ちません。なんどかメンテナンスを繰り返したら色も気にならなくなりました。こうした色や臭いについての気になる気にならないは個人の価値観で全然違うと思います。私はほとんど気にしません。
器も同様です。オイル仕上げの木の器は、油っぽいものや水気のあるもには使わない方が良いと思っている方も多いはずです。確かにシミができたりしますが、何度も使っていくうちに段々目立ちにくくなっていきます。シミの原因にもなりますが、油は木に染み込んで器に油分を与えてくれます。こうした油分が溜まっていくうちに段々とシミにも強くなっていきます。

オイル仕上げのタモ材の器に豚の生姜焼きをのせています。こうした油っぽい料理をのせても全く問題ありません。シミはつく可能性がありますが、ついても気にせず使い続けていくとだんだんとシミも目立ちにくくなります。使用する前に油がついたキッチンペーパーで軽く拭いてあげるとシミもつきにくくなります。私は使用前に軽く水でぬらして拭いてから使用しています。それでも少しはシミがつきにくくなると思います。私は汁物もオイル仕上げの器に入れています。油っぽい料理と同様に使用しています。
木の器の良い所は、いくつかあります。熱伝導率が低いので、器自体が熱くなりにくいです。汁物には陶器ではなく漆器や木の器が使われるのはそのためです。陶器や鉄製品だと熱くて持てなくなってしまいます。これはスプーンなどでも同様です。私は味噌汁の味見をするときに鉄のスプーンで味見しようとしてよく口の中を火傷をしていました。でも、木のスプーンを使えばそういうこともなくなります。
もう一つは軽いこと。木は重いイメージがありますが、意外と軽いです。木のカトラリーや器を持ってみるとその軽さに驚くことがあります。陶器に比べるとだいぶ軽い印象を受けます。軽いだけでなく割れにくくもあります。陶器は落としたりぶつけたりしたらかなりの確率で割れたり欠けたりしてしまいます。そして欠けた部分が鋭利なので、使えなくなってしまいます。その点、木のカトラリーや器は割れたり、欠けたりしにくいです。少し落としたり、ぶつけたぐらいでは欠けることはありません。万が一欠けたり割れたりしても刺さって怪我をしたりするリスクは少ないです。本格的な修理は専門家でなければできませんが、ヤスリで削ってカタチを整えたりすればとりあえず使えるようになります。

こちらも自作のチェリー材のお皿です。変わったカタチをしています。が、元々は丸いお皿だったんです。制作中に薄くしすぎて割れてしまいました。そこで薄くなりすぎた部分を落としてヤスリでカタチを整えました。結果として個性的なカタチになって自分でも気に入っています。木の器ではこんなこともできるんです。
最近では多くの木工作家さんがオイル仕上げのカトラリーやうつわを制作しています。
こちら私が 神宮前にある「shizen」という器やさんでのグループ展で購入した前田洋工作室さんの豆皿です。前田さんは以前にソリウッドの木工教室に通っていらっしゃいました。現在は木の器をメインに作
る木工作家として活動しています。陶器をメインに扱う器やさんでも木のカトラリーや器が展示されていることもあります。各地で開催されているクラフトフェアに行けば木のカトラリーや器を販売している作家さんはひとりはいるはずです。まだ、こうした木の器を使用した事がない方はぜひ一度使ってみてください。ハマる人はハマるはず…
瑞木@相模湖
注意:このブログ内で掲載した木の器やカトラリーは私個人の私物です。ソリウッドではこうしたカトラリーや器の販売はしていませんのでご了承ください。
-
- 2025年8月 (4)
- 2025年7月 (8)
- 2025年4月 (6)
- 2025年3月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (6)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (1)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (4)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (5)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (5)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (3)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (6)
- 2020年4月 (10)
- 2020年3月 (6)
- 2020年2月 (7)
- 2020年1月 (10)
- 2019年12月 (8)
- 2019年11月 (12)
- 2019年10月 (8)
- 2019年9月 (3)
- 2019年7月 (7)
- 2019年6月 (21)
- 2019年5月 (16)
- 2019年4月 (21)
- 2019年3月 (21)
- 2019年2月 (19)
- 2019年1月 (25)
- 2018年12月 (23)
- 2018年11月 (30)
- 2018年10月 (25)
- 2018年9月 (24)
- 2018年8月 (25)
- 2018年7月 (30)
- 2018年6月 (32)
- 2018年5月 (31)
- 2018年4月 (32)
- 2018年3月 (31)
- 2018年2月 (29)
- 2018年1月 (32)
- 2017年12月 (32)
- 2017年11月 (29)
- 2017年10月 (31)
- 2017年9月 (30)
- 2017年8月 (31)
- 2017年7月 (31)
- 2017年6月 (30)
- 2017年5月 (31)
- 2017年4月 (30)
- 2017年3月 (31)
- 2017年2月 (28)
- 2017年1月 (31)
- 2016年12月 (30)
- 2016年11月 (30)
- 2016年10月 (31)
- 2016年9月 (30)
- 2016年8月 (30)
- 2016年7月 (32)
- 最近のブログ記事
- オンラインショップ
お問い合わせContact
- TEL:0422-21-8487
- 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-28-3 2F
(営業時間: 12:30〜18:00/定休日:火・水曜日)